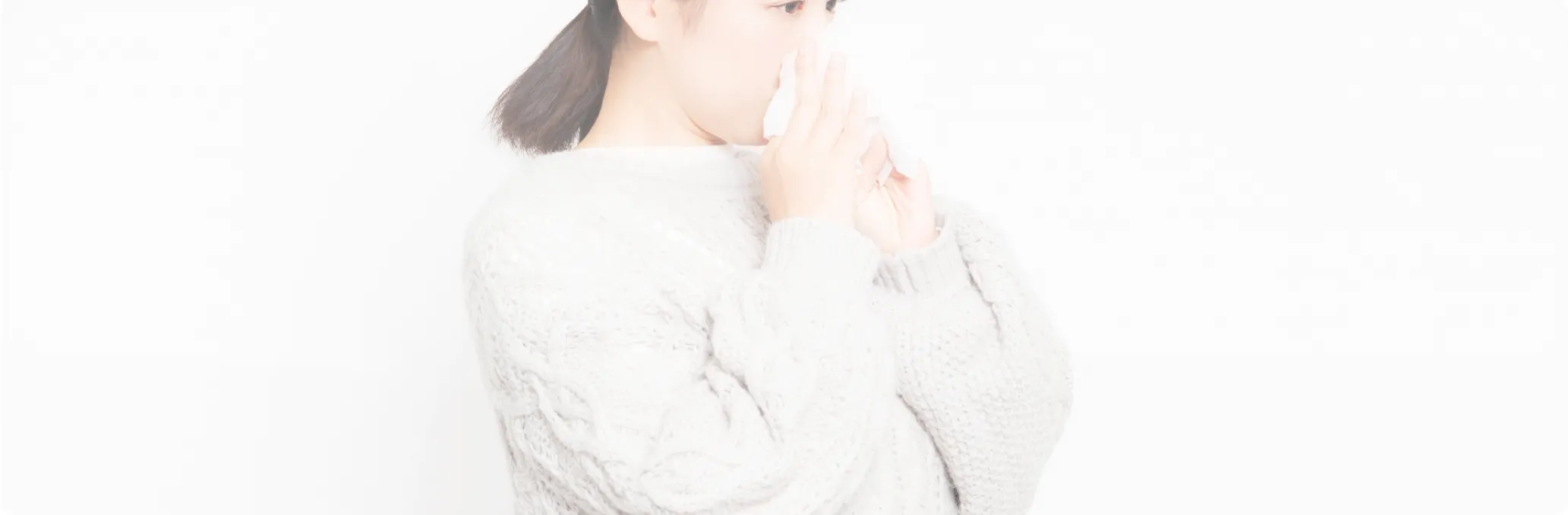肥満外来とは
肥満外来 は、健康的に体重を管理し、肥満が原因で発生するさまざまな病気を 予防・改善 するための専門的な診療を行う医療機関です。医師や専門スタッフが、食事・運動・生活習慣の指導を通じて、安全かつ効果的な減量をサポート します。
肥満とは?
肥満とは、体脂肪が過剰に蓄積した状態 を指します。特に BMI(ボディマス指数)が25以上 の場合、日本では肥満と定義されます。
肥満の分類(日本肥満学会基準)
| BMI | 肥満度 |
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5〜24.9 | 標準体重 |
| 25.0〜29.9 | 肥満(1度) |
| 30.0〜34.9 | 肥満(2度) |
| 35.0〜39.9 | 肥満(3度) |
| 40.0以上 | 肥満(4度) |
肥満が進行すると、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患 などの 生活習慣病のリスクが高まります。
肥満の原因
肥満は、主に 摂取カロリーと消費カロリーのバランスが崩れる ことで発生します。
主な原因
- 過剰なカロリー摂取(高カロリーの食事、過食、間食の増加)
- 運動不足(基礎代謝の低下、活動量の減少)
- ストレス・ホルモン異常(ストレスによる暴飲暴食、ホルモンバランスの乱れ)
- 遺伝的要因(家族に肥満の人が多い場合、発症リスクが高まる)
- 睡眠不足(睡眠不足が食欲増進ホルモンを増やし、肥満を促進)
- 生活習慣の乱れ(夜食、アルコール摂取、外食の頻度増加)
肥満のリスク
生活習慣病のリスク増加
- 糖尿病:インスリン抵抗性が高まり血糖値が上昇
- 高血圧:血圧が上がり、脳卒中・心筋梗塞のリスク増加
- 脂質異常症:悪玉コレステロール(LDL)の増加
- 動脈硬化:血管が硬くなり、心疾患リスクが高まる
運動器疾患
- 関節炎・腰痛:体重の負担増加で関節が痛みやすくなる
睡眠障害
- 睡眠時無呼吸症候群:脂肪が気道を圧迫し、呼吸が停止することがある
ホルモンバランスの乱れ
- 月経不順・不妊:女性ホルモンのバランスが崩れやすくなる
肥満外来での治療内容
肥満外来では、医師の診察のもと、個別の体質や生活習慣に応じた治療プランを提案 します。
1. 生活習慣改善指導
- 栄養指導:管理栄養士がバランスの良い食事のアドバイスを行う
- 運動指導:無理のない範囲での運動習慣を提案
- ストレス管理:メンタル面のサポートやリラクゼーション法を指導
2. 医療的アプローチ
- 薬物療法:食欲抑制剤や脂肪吸収抑制薬の処方
- GLP-1受容体作動薬:食欲を抑え、血糖値を改善する新しい治療法
肥満の予防と管理
1. 食生活の見直し
- 低カロリー・高たんぱくの食事を意識する
- 野菜・食物繊維を多く摂る
- 適切な食事量と食事回数を守る
- 間食・甘い飲み物を控える
2. 適度な運動
- ウォーキングやジョギングを習慣化
- 筋トレを取り入れ、基礎代謝を向上させる
- 運動の楽しさを見つけ、継続しやすい方法を選ぶ
3. 睡眠の質を向上
- 1日7時間以上の質の良い睡眠を確保
- 寝る前のスマホ・カフェイン摂取を控える
4. ストレス管理
- 趣味やリラクゼーションを取り入れ、心の安定を保つ
- ストレスによる過食を防ぐための対策を立てる
まとめ
肥満外来は、専門的な診療を通じて安全に体重管理を行い、生活習慣病の予防・改善をサポートする医療機関です。肥満の主な原因は、過剰なカロリー摂取、運動不足、ストレス、ホルモン異常、睡眠不足などが挙げられます。
治療では、生活習慣の改善指導や薬物療法を組み合わせ、個々に最適なプランを提供。肥満予防には、バランスの良い食事、適度な運動、良質な睡眠、ストレス管理が重要です。健康的な体重維持で、生活習慣病リスクを減らし、より良い生活を目指しましょう。
FAQ
よくあるご質問
- Q
- どのような検査や診断を行っていますか?
- A
- 当院では、耳鼻咽喉科・内科・皮膚科領域の検査や診断方法を提供しています。
- Q
- 花粉症で毎年悩まされています。どうしたら症状が軽減されますか?
- A
- 症状が出てから治療を開始するよりも、花粉が飛ぶ前から薬を予防的に内服すると効果がいいとされ奨励されています。また、通年での治療になりますが、「舌下免疫療法」で症状の改善が期待できます。
- Q
- 自分(親)が受診したいのですが、その間子供の面倒を見てもらえますか?
- A
- 短時間であればスタッフが見ますので遠慮せずご相談ください。ただし処置や検査などで時間がかかると予想される場合や、お子さんが騒いだりしてスタッフが面倒をみれない場合は事故防止のため、他の病院で診察をお願いしたり、もしくはお子さんを他の方に預かっていただき、再度改めてご本人だけで来院をお願いすることもありますのでご了承ください。
- Q
- 予約は必要ですか?
- A
- お電話または予約システムよりご予約下さい。