当院のコラムは全て
医師が監修しております。

ふくろうの森クリニック
院長 山田正人
2025.01.30

糖尿病の予防に向けて、毎日の生活で少しでも気を付けたいと思っている方へ。
糖尿病とは血液中にブドウ糖が増えてしまう病気のこと。糖尿病は進行するとさまざまな合併症を引き起こす、リスクの高い病気です。
糖尿病を予防するには、日々の生活で食事や運動が大事です。この記事では糖尿病を予防するために心がけたい生活習慣を具体的に解説します。
「最近、血糖値が気になる…」「糖尿病を予防したい!」という方はぜひ、この記事を参考にしてください。
目次
糖尿病とは?血液中にブドウ糖が増えてしまう病気
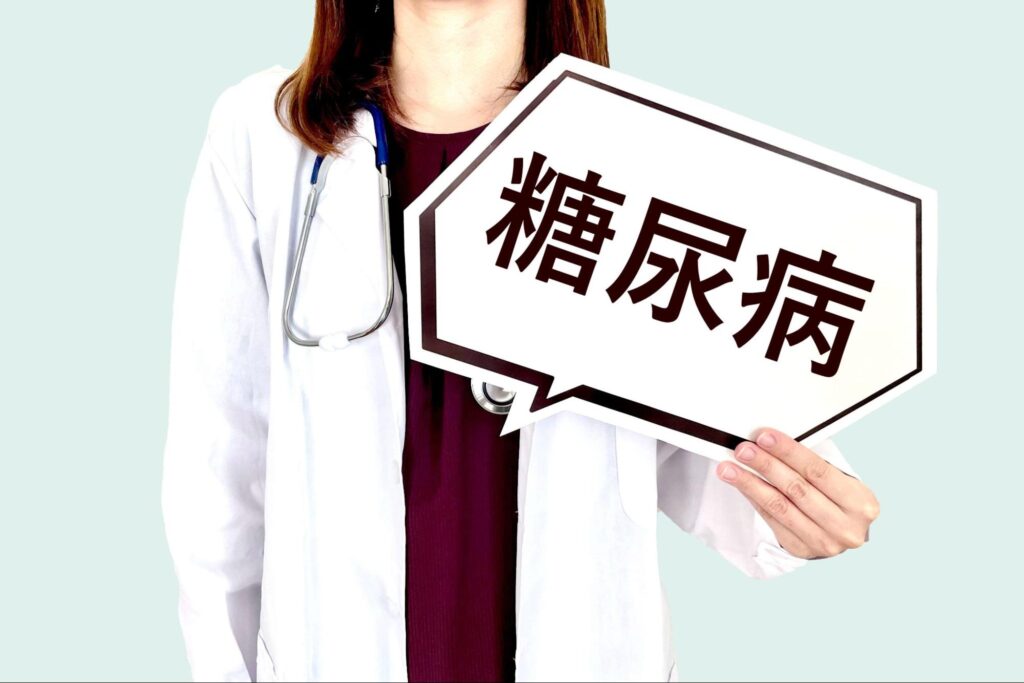
糖尿病とは、常に血糖値が高い状態が続く病気のこと。血糖値を下げるホルモン「インスリン」が十分に分泌されない、インスリンにより血糖値が十分に下がらないことによって発症します。
糖尿病には1型と2型があります(※1)。1型は先天的な原因や疾患によりインスリンを作る細胞が壊れてしまい、インスリンが分泌されない状態のこと。若年層に多く、1型糖尿病を発症するとインスリンを注射して補充する必要があります。
2型は生活習慣や体質によりインスリンが十分に効かず血糖値が下がらない状態のことで、中高年に多くみられるタイプです。治療には食事療法や運動療法のほか、必要に応じて内服薬やインスリン注射を行います。
(※1 参考)糖尿病とは|糖尿病情報センター
食事で気を付けるポイント

血糖値をコントロールするために、食事は必要不可欠なポイントです。食事で気を付けたいポイントを3点まとめました。
- 規則正しく3食食べる
- 栄養バランスの整った食事をとる
- 腹八分目を心がける
それぞれのポイントについて、理由や具体例を解説します。
規則正しく3食食べる
カロリーを抑えたい、忙しいなどの理由で食事を抜くのは良くありません。食事をとらず血糖値が低い状態が続くと、次の食事でエネルギーを取り込もうとするため血糖値が急上昇するリスクがあります。
朝昼夜と規則正しく、3食しっかり食べることを心がけましょう。
栄養バランスの整った食事をとる
糖尿病の予防には、食事の量だけでなく質も大切です。炭水化物を控えめにし、野菜や穀類、海藻やきのこを多く摂りましょう。食物繊維は小腸で栄養素の吸収を穏やかにするため、血糖コントロールに有効であると言われています(※1)。
調理も揚げ物、炒め物を控えて茹で料理・蒸し料理を選ぶと脂質や炭水化物を抑えられます。
(※1 参考)糖尿病ガイドライン2024 3章 食事療法|日本糖尿病学会
腹八分目を心がける
食べる量は腹八分目が目安です。満腹になるまで食べると、カロリーオーバーになってしまう可能性があります。
また、しっかり満腹中枢を働かせるために早食いは避け、よく噛んで食べましょう。1口につき30回噛むのが目安と言われています。
運動で気を付けるポイント

糖尿病の予防には食事だけでなく、運動も大事です。運動で気を付けるポイントをまとめました。
- 日常生活でこまめに体を動かす
- ジョギング、散歩を取り入れる
- 筋トレをする
アスリートのように強度の高い運動を毎日こなそうと思っても、なかなか続きません。日々できることから始めてみましょう。
なお、肥満や心血管系の病気を持っている方や高齢者の方は、運動により心臓や関節に負担がかかる可能性があります。運動を始める前に、必ず主治医と相談しましょう。
日常生活でこまめに体を動かす
日常生活の中でも、運動を取り入れる機会はあります。運動はブドウ糖をエネルギー源として消費する効果が期待できます。
例えば通勤時にエレベーターやエスカレーターではなく階段を使ったり、最寄りから少し手前の駅・バス停で降りて歩いたりすると運動量を増やせるでしょう。歩数計を使って、1日の歩数を測定し、目標の歩数を設定すると日々の運動量が数字でわかります。
ジョギング、散歩を取り入れる
ジョギング、散歩などの有酸素運動は体内のエネルギーを使い、消費カロリーを増やします。糖尿病ガイドラインでは週に150分(3日以上にわたり、活動しない日が連続して2日を超えないように)の運動が推奨されています(※1)。
肥満や高齢により関節への負担が気になる方は、プールの中で歩く水中ウォーキングがおすすめです。
(※1 参考)糖尿病ガイドイン2024 4章 運動療法|日本糖尿病学会
筋トレをする
有酸素運動だけでなく、筋トレ(レジスタンス運動)も糖尿病に対して効果があると言われています。糖尿病ガイドラインでは連続しない日程で週に2〜3回のレジスタンス運動が推奨されています(※1)。
人により適切なトレーニングは異なりますので、無理のない程度の負荷で筋トレを取り入れるとよいでしょう。
(※1 参考)糖尿病ガイドイン2024 4章 運動療法|日本糖尿病学会
食事、運動以外で気を付けるポイント

食事、運動のほか、糖尿病を予防するために気を付けたいポイントについて解説します。
- ストレスを発散する
- 禁煙する
- 適正体重を保つ
ストレスを発散する
うつ病(うつ傾向)やストレスが2型糖尿病の発症リスクを高めることが、これまでの研究でわかっています(※1)。なるべくストレスをこまめに発散し、ストレスをためない生活を心がけましょう。
リフレッシュできる趣味や熱中できることがあると、ストレスを感じても息抜きになります。
(※1 参考)21章 2型糖尿病の発症予防|日本糖尿病学会
禁煙する
たばこを吸う人は、他の要因を考慮しても2型糖尿病に1.4倍かかりやすいことが報告されています(※1)。糖尿病を予防するために、現在たばこを吸っている人は禁煙しましょう。
たばこは糖尿病以外の生活習慣病や、喘息・COPDなどの呼吸器疾患の発症にもつながります。いきなり禁煙するのが難しければ徐々に本数を減らす、ニコチン製剤を利用するなどの工夫も有効です。
自力で禁煙が難しければ、禁煙外来の受診も検討しましょう。
適正体重を保つ
肥満は糖尿病のリスク要因です。BMI 25以上の肥満、特に内臓脂肪型の肥満は糖尿病の発症や進行・悪化を助長するため、適正な体重をキープすることで糖尿病を予防する効果が期待できます。
日本肥満学会では、BMI 22を適正体重としています。BMIとはBody Mass Indexの略で、体重を身長(m)の2乗で割ることで算出される数値です。
生活習慣の改善により2kg減量できれば、糖尿病のリスクを減らせると言われています(※1)。
(※1 参考)21章 2型糖尿病の発症予防|日本糖尿病学会
まとめ

今回は糖尿病を予防するために食事、運動をはじめとした生活習慣で気を付けるべきポイントをまとめました。
糖尿病は根本的な治療が難しい病気です。糖尿病と診断されていなくても、血糖値が気になった段階で予防を心がけましょう。
また、糖尿病は初期症状がほとんどなく、悪化するとさまざまな合併症を引き起こす疾患です。定期的に健康診断を受け、結果から受診が推奨された場合は現時点で症状を感じていなくても放置せず医療機関を受診しましょう。
糖尿病の治療はふくろうの森のクリニックへ

ふくろうの森耳鼻咽喉科では、耳鼻咽喉科のほか内科を診療しています。花小金井駅から徒歩5分の場所にあり、ネット予約が可能です。
「糖尿病について医師に相談したいけど、どのクリニックに通うか迷っている…」という方は、当院でもご相談を承ります。お気軽にご来院ください。
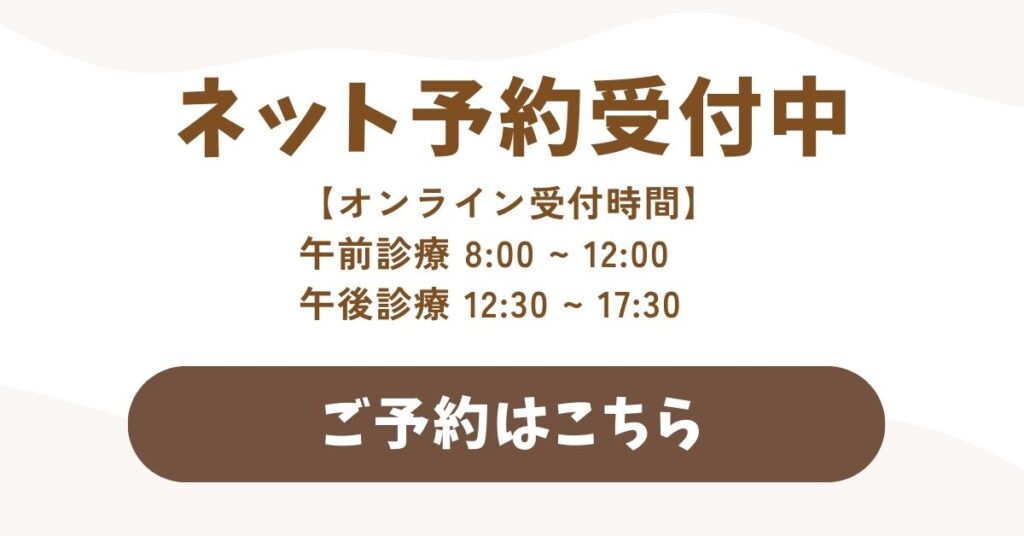
コラムを探す
おすすめのコラム
投稿がありません。
人気のコラム
コラムを探す



